肝障害とは?
肝障害とは、血液検査で「肝臓の働きを示す数値(肝機能検査)」に異常が見られる状態を指します。
主な検査項目は:
- AST(GOT), ALT(GPT):肝細胞のダメージを示す酵素
- γ-GTP(ガンマ・ジーティーピー):アルコールや脂肪肝で上がりやすい酵素
- ALP, 総ビリルビン:胆道(胆汁の通り道)の異常を示唆します。肝外臓器(総胆管、膵臓など)に原因があることも。
これらが高い=肝臓の細胞が壊れている、または炎症を起こしているサインですが、原因は多岐にわたり専門的な知識を持って精査する必要があります。
どんな原因があるの?
肝障害の原因はとても多岐にわたります。主なものは次の通りです。
| 分類 | 主な原因 | 備考 |
|---|---|---|
| 代謝機能障害性 | 脂肪肝(肥満・糖尿病・脂質異常症・アルコールなど) | 近年もっとも多い原因 |
| ウイルス性 | B型肝炎、C型肝炎など | 血液や体液を介して感染 |
| 薬物性 | 処方薬・市販薬・サプリメント・栄養ドリンクなど | 「健康食品」でも起こることあり |
| 自己免疫性 | 自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎など | 自分の免疫が肝臓を攻撃する病気 |
| 肝臓以外の誘因 | 胆膵疾患、甲状腺疾患など | 全身の評価が必要 |
| その他 | 代謝異常、遺伝性疾患など | 比較的まれだが見逃せない |
肝障害を指摘されたらどうすればいい?
① 肝臓専門医を受診する
上記のように肝障害の原因は非常に多岐にわたり診断が難しいだけでなく、それぞれ治療方法も異なるため、まずは肝臓専門医のいる施設での受診がおすすめです。肝臓内科、あるいは消化器内科を受診しましょう。
そして健診結果だけでは一時的な変化か、持続した異常なのか分かりませんので、なるべく早く再検査を受け「本当に異常が続いているか」を確認します。
② 原因特定に向けた詳細な血液検査を受ける
肝障害が持続していた場合は原因の特定を行います。
- 肝炎ウイルス(主にB型・C型)検査
- 脂質・血糖チェック(背景の代謝機能障害の評価)
- 薬・サプリ・アルコール摂取歴の確認
- 自己抗体検査
- 甲状腺ホルモン検査
など健診でチェックすることの少ない項目も見逃すことなくスクリーニングが必要です。結果が出揃うのにおおよそ1-2週間かかります。
なかには複数の原因が同時に存在する場合もあり、検査結果の解釈にも高度な専門性を要します。
③ 画像検査(腹部エコー)
腹部エコーは痛みや被爆を伴わない安全かつリアルタイムで結果がわかる検査です。
ここでは肝臓の形・脂肪の量・腫瘤の有無をチェックします。その他胆道や膵臓なども同時に観察し、肝臓以外の臓器が原因でないかもチェックします。
ただしエコーは術者の技量によって得られる情報の質と量に大変大きな差が生まれる検査です。
当院では肝臓専門医がエコー検査を行うため、見逃しなく確実に肝臓の状態を評価いたします。
④ 治療
肝障害はその原因と程度によって治療が全く異なります。
多くの場合1ヶ月毎の通院で治療の反応を見ながらオーダーメイドでの治療を行います。
病状が落ち着いた際は診察間隔を延ばしたり、薬物治療を終了することも検討します。
進行した肝硬変や肝がんが見つかった際には、提携している専門医療機関に紹介し精査と治療を実施してもらいます。慢性肝炎や初期~中期の肝硬変、肝がんの終末期(緩和治療)に関しては当院で対応可能です。
肝障害を放置するとどうなる?
多くの場合、肝障害を起こしていても自覚症状はありません。肝臓が「沈黙の臓器」と呼ばれる所以です。
しかしながら肝障害を放置すると、炎症の慢性化により 肝線維化(かんせんいか)をきたし、肝硬変や肝がんが発症する恐れがあります。
ちなみに肝硬変や肝がんを発症していたとしても、かなり進行するまでは無症状なのが恐ろしいところです。
肝障害は「無症状のうちに進む」のが最大の特徴です。
症状が出る前に正しく診断・治療を行うことで、多くの場合元気な肝臓を取り戻すことが可能です。
まとめ
健診で肝障害を指摘されたら、「症状がなくても精密検査」が鉄則です。
- 肝臓専門医を受診する
- 血液検査で原因の精密検査
- エコー検査で画像評価
- 適切な治療を行う
当院では経験豊富な肝臓専門医が診察~検査~治療まで一貫して行っております。安心してご相談ください。
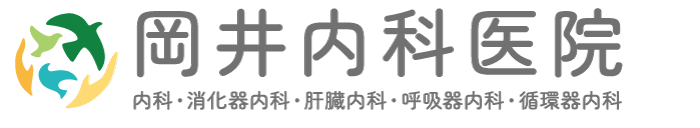
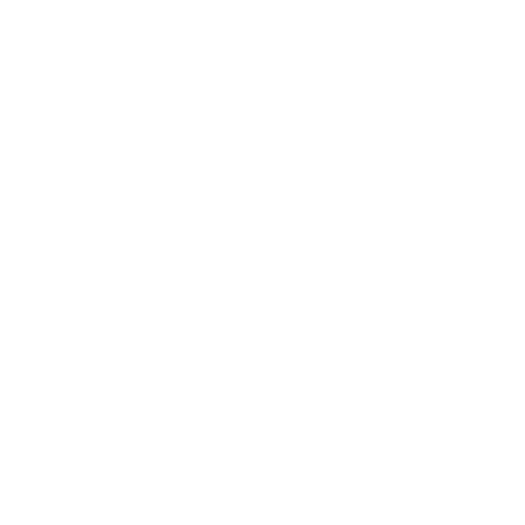 友だち追加
友だち追加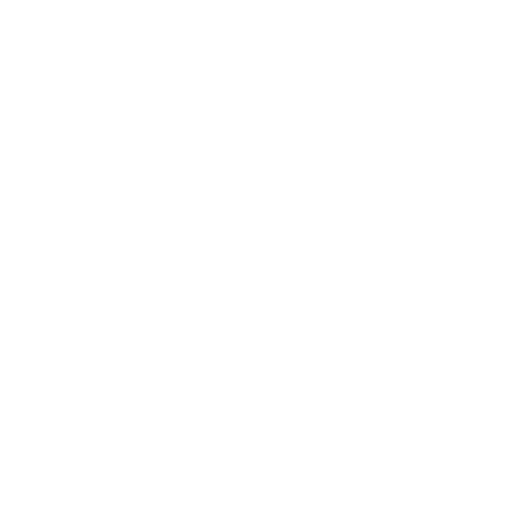 WEB予約
WEB予約 電話
電話